2025/6/23 識者の指摘により”ムチン”の記述を削除しました
夏が旬を迎える野菜には、暑い季節を乗り切るための栄養素がたっぷり含まれています。トマトやナス、ピーマンといった色鮮やかな夏野菜は、ビタミンやミネラルが豊富で、内側からの健康維持をサポートしてくれるのです。
さらに、夏は紫外線が強まる季節。日焼けによる肌ダメージだけでなく、体の疲労感や免疫力低下にも関わる紫外線から身を守るためには、外側からのケアと同時に、内側からの栄養補給が重要です。
この記事では、夏野菜の栄養素と健康効果、さらに紫外線対策としての役割まで詳しく解説します。毎日の食事に取り入れやすいレシピも紹介しますので、夏を元気に過ごすための参考にしてください。
夏野菜の種類と旬の時期について
夏野菜は豊富な水分と栄養を含み、暑い季節に体を内側から潤してくれます。これらの野菜は3つの分類に分けられ、それぞれ異なる栄養素と効能を持っています。旬の時期に収穫される夏野菜は、栄養価が高く、味も格別であることが特徴です。
果菜類・葉菜類・根菜類の特徴と栄養
夏野菜は大きく3つのカテゴリーに分けられますが、それぞれに特徴的な栄養素と効能があります。まず果菜類は、植物の実の部分を食べる野菜で、水分含有量が多く、ビタミンやミネラルが豊富です。
果菜類には、トマト、なす、きゅうり、ピーマン、ゴーヤ、トウモロコシ、オクラ、ズッキーニなどが含まれます。これらは夏の代表的な野菜で、特にトマトはリコピンという強力な抗酸化物質を含み、紫外線ダメージから細胞を守る効果があります。
- 果菜類:トマト、なす、きゅうり、ピーマン、ゴーヤ、トウモロコシ、オクラ、ズッキーニ
- 主な栄養素:ビタミンC、ビタミンA、カリウム、リコピン
- 特徴:水分が多く、体を冷やす効果があり、夏バテ予防に最適
次に葉菜類は、植物の葉の部分を食べる野菜です。夏の葉菜類には、ニラ、レタス、空芯菜、モロヘイヤ、大葉などがあります。これらは鉄分やカロテンを豊富に含み、血液の健康維持や免疫力向上に役立ちます。
モロヘイヤは「食べる輸血」と呼ばれるほど鉄分が豊富で、夏の疲れによる貧血予防に効果的です。大葉には抗菌作用があり、食中毒予防の点でも夏に重宝します。
- 葉菜類:ニラ、レタス、空芯菜、モロヘイヤ、大葉、アスパラガス
- 主な栄養素:鉄分、葉酸、カロテン、ビタミンK
- 特徴:光合成によって作られた栄養素が豊富で、体の酸化を防ぐ
最後に根菜類は、植物の根の部分を食べる野菜です。夏の根菜類には新しょうが、みょうが、にんにく、ビーツなどがあります。これらは食物繊維が豊富で、腸内環境を整え、体の余分な熱や水分を排出する作用があります。
新しょうがには発汗作用と殺菌作用があり、体の熱を下げる働きがあるため、夏バテ予防に最適です。にんにくにはアリシンという成分が含まれ、疲労回復や免疫力向上に効果的です。

夏が旬の野菜カレンダー
夏野菜の多くは6月から8月にかけて旬を迎えますが、それぞれの野菜によって最も美味しく栄養価の高い時期は少しずつ異なります。旬の時期を知ることで、より効果的に栄養を摂取することができます。
6月から8月にかけて旬を迎える代表的な野菜には、トマト、きゅうり、オクラ、ニラ、空芯菜、にんにくなどがあります。これらは夏の全期間を通して楽しめる野菜です。
| 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|
| 果菜類 | トマト、きゅうり、オクラ、ピーマン | トマト、なす、きゅうり、ゴーヤ、トウモロコシ、ズッキーニ | トマト、なす、きゅうり、ゴーヤ、トウモロコシ |
| 葉菜類 | ニラ、空芯菜、モロヘイヤ、アスパラガス | ニラ、レタス、空芯菜、モロヘイヤ、大葉 | ニラ、レタス、空芯菜、モロヘイヤ |
| 根菜類 | にんにく、新しょうが、ビーツ、みょうが | にんにく、新しょうが、みょうが | にんにく、新しょうが、みょうが |
7月から8月にかけては、なす、ゴーヤ、ズッキーニ、トウモロコシ、大葉などが最盛期を迎えます。特にゴーヤは高温多湿を好む野菜で、7月から8月が最も栄養価が高くなります。
また、アスパラガスとビーツは初夏の6月から7月が旬であり、季節の変わり目に重宝する野菜です。これらは梅雨時期の湿気対策にも効果的な栄養素を含んでいます。
- 6月が旬のピーク:アスパラガス、ビーツ
- 7月が旬のピーク:なす、ズッキーニ、トウモロコシ、大葉
- 8月が旬のピーク:ゴーヤ、モロヘイヤ
- 6〜8月を通して旬:トマト、きゅうり、オクラ、ニラ、空芯菜、にんにく、新しょうが、みょうが
旬の野菜を選ぶことで、栄養価が高く、味も良い野菜を効率よく摂取することができます。また、旬の野菜は価格も手頃になりますので、家計の面でもメリットがあります。
夏野菜の栄養素が紫外線対策に役立つ理由
夏野菜には紫外線から私たちの体を守るための栄養素が豊富に含まれています。特に抗酸化物質は、紫外線によって生じる活性酸素を除去し、肌や細胞のダメージを軽減する効果があります。また、水分と電解質のバランスを整える栄養素も、夏の体調管理に重要な役割を果たします。

抗酸化作用で紫外線ダメージから細胞を守る
夏は紫外線が強まる季節であり、外出時の日焼け対策だけでなく、体の内側からのケアも重要です。紫外線を浴びると体内で活性酸素が発生し、これが細胞にダメージを与え、肌の老化や疲労感の原因となります。
夏野菜には、ビタミンC、ビタミンE、βカロテン、リコピンなどの抗酸化物質が含まれています。これらは活性酸素を除去し、紫外線による細胞ダメージを軽減する効果があります。
特にトマトに含まれるリコピンは強力な抗酸化作用を持ち、紫外線による肌ダメージを内側から防ぐ効果があります。トマトは加熱することでリコピンの吸収率が高まるため、夏の料理に積極的に取り入れることをおすすめします。
- ビタミンC:肌の生成に関わり、シミやしわの予防に効果的(ピーマン、トマト、オクラ)
- βカロテン:皮膚や粘膜を保護し、日焼けによるダメージを軽減(ニンジン、モロヘイヤ)
- リコピン:強力な抗酸化作用で細胞を守る(トマト)
- ビタミンE:細胞膜を保護し、肌の老化を防ぐ(アスパラガス、モロヘイヤ)
ピーマンはビタミンCの含有量がレモンの約2倍あり、肌の健康維持に大きく貢献します。また、モロヘイヤにはβカロテンとビタミンEが豊富に含まれており、紫外線によるダメージから肌を保護します。
これらの抗酸化物質を含む野菜を日常的に摂取することで、紫外線による体へのダメージを軽減し、夏の疲れを防ぐことができます。外側からのUVケアと併せて、内側からのケアも意識することが大切です。
水分と電解質バランスで熱中症・夏バテ予防
夏は汗をかきやすく、水分と電解質のバランスが崩れやすい季節です。特に紫外線を浴びると体温が上昇し、さらに発汗が促進されます。このとき、水分だけでなく、カリウムやナトリウムなどの電解質も失われるため、これらを補給することが重要です。
夏野菜の多くは水分含有量が高く、同時に電解質も豊富に含んでいます。きゅうりは約95%が水分で構成されており、体の熱を下げる効果があります。また、カリウムも含まれているため、塩分バランスの調整にも役立ちます。
トマトやズッキーニにも水分が多く含まれており、同時にカリウムも豊富です。カリウムは体内のナトリウム(塩分)バランスを整え、むくみの軽減や血圧の安定化に寄与します。
- 水分が豊富な夏野菜:きゅうり(約95%)、トマト(約94%)、レタス(約96%)、ズッキーニ(約95%)
- カリウムが豊富な夏野菜:ゴーヤ、トマト、ズッキーニ、オクラ
- ナトリウムとのバランスを整える効果:むくみの軽減、血圧の安定化
ゴーヤに含まれるカリウムは、体内の余分な塩分を排出する作用があり、夏のむくみ解消に効果的です。また、ゴーヤに含まれるビタミンCは熱に強く、炒め物にしても栄養素が損なわれにくいという特徴があります。
夏野菜を日常的に摂取することで、水分と電解質のバランスを整え、熱中症や夏バテのリスクを軽減することができます。特に紫外線の強い日に外出する際は、事前に水分と電解質を十分に補給することが重要です。UVカットのフェイスカバーなどで外側から守りながら、内側からも夏野菜の栄養でケアすることで、より効果的に夏の健康を維持できます。
代表的な夏野菜の健康効果と活用法
夏が旬を迎える野菜は種類が豊富で、それぞれに特有の栄養素と健康効果があります。これらの野菜を日常的に摂取することで、紫外線対策や夏バテ予防など、夏特有の健康課題に対応することができます。ここでは、代表的な夏野菜の効能と、効果的な摂取方法について詳しく見ていきましょう。
トマト・ピーマン・なすの栄養パワー
夏野菜の代表格であるトマト、ピーマン、なすには、夏の健康維持に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。これらの野菜は単体でも美味しく、組み合わせることでさらに栄養バランスの良い料理になります。
トマトには強力な抗酸化物質であるリコピンが含まれており、紫外線によるダメージから細胞を守る効果があります。リコピンは脂溶性のため、オリーブオイルなどの油と一緒に調理すると吸収率が高まります。また、ビタミンCやビタミンAも豊富で、肌の健康維持や免疫力向上に寄与します。
- トマトの主な栄養素:リコピン、ビタミンC、ビタミンA、カリウム
- 効能:抗酸化作用、免疫力向上、肌の健康維持、むくみ解消
- 効果的な摂取法:オリーブオイルと組み合わせる、加熱調理する
ピーマンはビタミンCが非常に豊富で、100gあたり約150mgを含み、これはレモンの約2倍に相当します。ビタミンCは紫外線によるダメージから肌を保護し、コラーゲンの生成を促進します。また、βカロテンも含まれており、抗酸化作用により細胞を守ります。
ピーマンのビタミンCは熱に弱いため、短時間で調理するか、生で食べることで栄養素を効率的に摂取できます。彩りのきれいな赤や黄色のパプリカはビタミンCやβカロテンがさらに豊富です。
- ピーマンの主な栄養素:ビタミンC、βカロテン、ビタミンE、食物繊維
- 効能:抗酸化作用、免疫力向上、肌の健康維持、腸内環境改善
- 効果的な摂取法:短時間調理、生食(細かく刻んでサラダに)
なすには「ナスニン」という強力な抗酸化物質が含まれており、特に皮の部分に多く含まれています。ナスニンは紫外線による活性酸素の発生を抑え、肌の老化を防ぐ効果があります。また、カリウムも豊富で、夏の汗による塩分バランスの乱れを整える作用があります。
なすは油との相性が良く、揚げ物や炒め物にすることで、ナスニンの吸収率が高まります。ただし、吸油性が高いため、ヘルシーに摂りたい場合は蒸し調理もおすすめです。
- なすの主な栄養素:ナスニン、カリウム、食物繊維、ビタミンB1
- 効能:抗酸化作用、むくみ解消、腸内環境改善、エネルギー代謝促進
- 効果的な摂取法:皮ごと調理、油と組み合わせる

ゴーヤ・オクラ・きゅうりの健康効果
ゴーヤ、オクラ、きゅうりは夏特有の健康課題に対応する栄養素を豊富に含んでおり、特に体を冷やす効果や水分補給、腸内環境の改善に役立ちます。これらの野菜を積極的に摂取することで、夏バテ予防や紫外線対策に効果的です。
ゴーヤにはビタミンCが豊富に含まれており、特に熱に強いという特徴があります。通常のビタミンCは加熱によって失われやすいですが、ゴーヤのビタミンCは炒め物などの調理でも栄養素を保ちます。また、モモルデシンやチャランチンという成分が含まれており、血糖値の上昇を抑える効果があります。
- ゴーヤの主な栄養素:ビタミンC、カリウム、モモルデシン、チャランチン
- 効能:抗酸化作用、血糖値コントロール、食欲増進、むくみ解消
- 効果的な摂取法:油と炒める、塩もみして苦味を和らげる
オクラに含まれる食物繊維(ガラクタン、アラバン)は水溶性と不溶性の両方を含み、腸内環境を整える効果があります。また、ネバネバ成分は胃の粘膜を保護し、消化を助ける作用があります。ビタミンB1も含まれており、エネルギー代謝を促進し、夏の疲労回復に役立ちます。
オクラは加熱しすぎるとネバネバ成分が失われるため、さっと茹でるか、生のまま酢の物にするのがおすすめです。また、ヘタの部分にはポリフェノールが多く含まれているため、ヘタの近くまで食べるとより栄養を摂取できます。
- オクラの主な栄養素:食物繊維(ガラクタン、アラバン)、ビタミンB1、ビタミンC
- 効能:腸内環境改善、胃粘膜保護、疲労回復、免疫力向上
- 効果的な摂取法:短時間加熱、酢の物、ヘタの近くまで食べる
きゅうりは水分含有量が約95%と非常に高く、体を冷やす効果があります。カリウムも含まれており、体内の塩分バランスを整え、むくみを解消する作用があります。また、ビタミンKが豊富で、骨の健康維持に役立ちます。
きゅうりは生で食べることが多いですが、塩もみすることでよりカリウムの効果を発揮します。また、皮にはビタミンKが多く含まれているため、皮ごと食べるのがおすすめです。
- きゅうりの主な栄養素:水分、カリウム、ビタミンK、食物繊維
- 効能:体温調整、むくみ解消、骨の健康維持、腸内環境改善
- 効果的な摂取法:皮ごと食べる、塩もみする、冷やして食べる
夏野菜を活かした簡単レシピ
夏野菜を毎日の食事に取り入れるための簡単で栄養満点のレシピをご紹介します。これらのレシピは、紫外線対策や夏バテ予防に効果的な栄養素を効率よく摂取できるよう工夫されています。
まず、「ナスとズッキーニの焼き浸し」は、抗酸化物質が豊富なナスと水分が多いズッキーニを組み合わせた夏におすすめの一品です。オリーブオイルでナスとズッキーニを焼き、醤油とみりんで作ったタレに浸すことで、ナスニンの吸収率を高めます。冷蔵庫で冷やして食べると、さらに夏バテ予防効果が高まります。
- 材料:ナス、ズッキーニ、オリーブオイル、醤油、みりん、かつお節
- 調理時間:約15分
- 栄養効果:抗酸化作用、むくみ解消、体温調整
次に、「アボカドとトマトとサーモンのマリネ」は、リコピンが豊富なトマトと良質な脂質を含むアボカドとサーモンを組み合わせた栄養バランスの良いレシピです。トマトのリコピンは脂質と一緒に摂ることで吸収率が高まるため、このレシピは理想的な組み合わせと言えます。
アボカドやサーモンに含まれるオメガ3脂肪酸は、紫外線による炎症を抑える効果があり、トマトのリコピンと相乗効果を発揮します。レモン汁で爽やかに味付けすることで、ビタミンCの追加摂取も可能です。
- 材料:トマト、アボカド、サーモン(刺身用)、レモン汁、オリーブオイル、塩、黒こしょう
- 調理時間:約10分
- 栄養効果:抗酸化作用、抗炎症作用、良質なタンパク質と脂質の摂取
最後に、「豚肉と2色ピーマンのオイスター炒め」は、ビタミンCが豊富なピーマンと良質なタンパク質を含む豚肉を組み合わせたスタミナ料理です。赤と緑のピーマンを使うことで、見た目も鮮やかに仕上がります。豚肉に含まれるビタミンB1は疲労回復に効果的で、夏バテ予防に役立ちます。
オイスターソースで味付けすることで、うま味が増し、食欲が落ちる夏でも美味しく食べられます。短時間で炒めることで、ピーマンのビタミンCの損失を最小限に抑えられます。
- 材料:豚肉(薄切り)、緑ピーマン、赤ピーマン(または赤パプリカ)、オイスターソース、酒、片栗粉
- 調理時間:約15分
- 栄養効果:ビタミンC補給、疲労回復、タンパク質摂取
これらのレシピは短時間で作れるものばかりですので、忙しい日でも手軽に栄養たっぷりの夏野菜料理を楽しむことができますよ。夏野菜を積極的に取り入れて、内側から紫外線対策と健康維持を心がけてみてください。

まとめ

夏が旬を迎える野菜には、私たちの健康を内側からサポートする豊富な栄養素が含まれています。果菜類、葉菜類、根菜類と分類される夏野菜は、それぞれに特有の栄養素と効能を持ち、夏の健康課題に対応する力を秘めています。
特に紫外線対策という観点では、トマトのリコピン、ピーマンのビタミンC、ナスのナスニンなどの抗酸化物質が、紫外線によるダメージから細胞を守る重要な役割を果たします。外側からのUVケアと併せて、内側からも夏野菜の栄養で守ることが理想的です。
また、水分と電解質のバランスを整えるきゅうりやズッキーニ、カリウムが豊富なゴーヤやトマトは、夏バテや熱中症予防に効果的です。これらの野菜を日常的に摂取することで、暑い季節を元気に乗り切ることができます。
紹介したレシピを参考に、夏野菜を積極的に食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。旬の時期に収穫される野菜は栄養価が高く、味も格別です。内側からのケアと外側からの紫外線対策を組み合わせることで、より効果的に夏の健康を維持することができます。この夏は、栄養たっぷりの夏野菜を味方につけて、健やかで元気な毎日を過ごしてみてください。


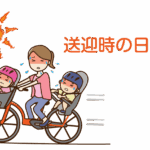

コメント
(速報)京都大学医学部附属病院 よりお詫びと訂正(2025年3月21日)- 公共メディアじゃんぬ –
〔訂正〕
京大病院広報124号において、 オクラには、ムチンが含まれている旨説明しておりましたが、
オクラにムチンは含まれておらず、また、植物全般にムチンは存在しません。
誤った記述がございましたので、ここに訂正いたします。
【参考】公益社団法人 日本食品科学工学会『食品工業辞典』(日本食品工業学会編、昭和54年・第1版発行)における用語解説の訂正
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/relation/publish.html
#じゃんぬねっと
#渡邊渚
ご指摘ありがとうございます。
確認の上修正させて頂きます。